〒669-1133 兵庫県西宮市東山台3丁目4番地11(JR福知山線西宮名塩駅から徒歩10分 駐車場:駅前にあり)
10:00~20:00(年末年始・春季・秋季を除く)
家族信託

家族信託を依頼できる専門家
- 弁護士: 家族信託に関する法律相談や信託契約書の作成を行うことができます。法律事務に特化しているため、複雑な問題にも対応可能です。必要に応じて提携弁護士をご紹介いたします。
- 司法書士: 不動産登記や契約書の作成など、手続きに関する業務を行います。法律相談はできませんが、実務的なサポートが得られます。必要に応じて提携司法書士をご紹介いたします
- 税理士: 家族信託に関連する税務相談や相続税対策についてアドバイスを提供します。税務面での専門知識が必要な場合に適しています。
- 信託銀行や不動産会社: 家族信託の設計や運用を行うことができる場合があります。特に不動産に関する信託を考えている場合に有用です。必要に応じて提携信託銀行をご紹介いたします。
家族信託の概要
家族信託の仕組み

家族信託の基本的な関係は、「委託者」「受託者」「受益者」です。
- 「委託者」は、財産のもともとの所有者で、財産を信託する人
- 「受託者」は、財産の管理運用処分を任される人
- 「受益者」は、財産権を持ち、財産から利益を受ける人
委託者が財産の管理を受託者に任せ、その財産を受託者が管理し、その財産から発生した利益を受益者が得る仕組みになっています。家族信託では親のために子が財産を管理し、利益は所有者である親が得るなど、委託者と受益者が同じ人になることがほとんどです。
家族信託の背景

高齢化と認知症の問題があります。厚生労働省の「令和2年介護保険事業状況報告」によると、要介護認定者数は、65歳から74歳で全体の1割強ですが、75歳以上になると9割弱と急増しています。年齢が上がるにつれて認知症になる確率も急激に上昇します。認知症が悪化すると、銀行の口座などは凍結されてしまい、子どもでも親のお金を下ろせなくなります。そうすると、親の介護に手をあげた子どもが金銭的な負担も強いられることにつながります。このことから、少なくとも70歳頃までに、認知症に備えた対策が必要といえます。「自分の財産のことで、子どもに迷惑はかけられない」。そういったニーズから、家族の高年齢化に伴う様々なトラブルに柔軟に対応できる家族信託が広まってきています。
家族信託のメリット

1.財産管理が委託者の判断能力に影響されない
家族信託の背景には、親の認知症による財産凍結の問題があります。親が認知症などになり、財産を管理することが難しくなると、預金口座は凍結され、お金を下ろすことができなくなります。また、自宅などの不動産を売ることもできません。認知症が悪化した後にも利用できる対策として成年後見制度がありますが、親族が後見人に選ばれるとは限らないこと、財産の管理運用処分が制限をされることがあるなど、利用しづらい面があります。財産の名義を子どもに変えられること、広い裁量を与えられることが家族信託の大きなメリットです。
2.委託者の思い通りに財産の承継・事業継承を決定できる
家族信託のメリットの一つとして、遺言効果があります。これは、家族信託契約の中に、次に財産権(財産から利益を受ける権利)を継がせる人をあらかじめ定めておくことによって、その内容が法律上有効となり、遺言を残すことと同様の効果を得ることができます。また、次の後継者(2番目)だけでなく、次の次の後継者(3番目)以降を決めることもできます。これは遺言にはなく、家族信託でのみできることです。
3.遺族がハイリスクな不動産の共有をしなくて済む
家族信託が有効なケースの一つとして、親から受け継いだ収益不動産が兄弟での共有になっているケースがあります。例えば、収益不動産を兄弟ABCの3人で、それぞれ3分の1ずつ所有している場合です。これからも、不動産を第三者に貸すことで家賃収入を得たいと考えています。しかし、A、B、Cのうち、1人でも認知症になってしまい契約能力がなくなってしまうと、収益不動産の全体が凍結してしまう危険があります。新しい入居者との契約をする場合や、古くなってきたので大規模な修繕を行う場合には、所有者全員の意思が必要になるためです。そのため、高齢者同士の共有はとても危険です。3人で共有の場合にはリスクが3倍になると言えます。そこで、家族信託を活用しBとCの持ち分をAに信託をすることで、BとCの契約能力喪失の影響を受けずに、Aが1人で収益不動産の経営をすることができます。そして得た家賃収入は、全員が得ることができます。
4.成年後見制度より柔軟な取り決めもできる
家族信託では、成年後見制度よりも柔軟な財産管理ができます。成年後見制度では、本人の財産を守ることに重点が置かれます。言い換えれば、本人の財産を減らさないことが重要視されるため、それに反するような財産の管理をすることはできません。例えば、収益不動産の経営をしている大家さんや会社のオーナー兼社長が認知症になった場合、成年後見制度だと、本来であれば経営に必要である将来に向けた投資をすることができません。本人の財産を減らさないために、将来儲かるかどうかわからない投資を実行することはできず、攻めの経営が制限されます。この点、家族信託の場合には、子どもに大きな裁量を与えることができます。元の所有者(委託者)が財産管理の方向性を決めて、その方向性に沿って、子ども側は大きな裁量をもって柔軟に財産の管理運用処分をすることができます。そのため、上述のような、投資するなどの攻めの経営をすることも可能になります。一方で、家族信託は、受託者である子どもが大きな権限を持つことになるので、子どものことを信頼できない場合には、信託をすべきではないと言えるでしょう。
5.相続による遺族の負担を軽減できる
家族信託の遺言効果のもう一つの側面ですが、家族信託契約により承継者を決めておくことで、相続が発生した場合の遺産分割協議が不要になります。これは大きなメリットです。遺産分割協議では、相続人全員で話し合い、誰が何を相続するのかを決めなくてはいけません。しかし、相続人の間で意向が揃わなかったり、相続人の1人が認知症等により話し合いをすることができない場合には、相続の手続きはスムーズにできなくなります。渡す側の親が財産の承継についてあらかじめ決めておくことは、認知症や相続争いによる遺産の凍結を防ぐための、最も有効な方法であると言えるのです。
6.倒産隔離機能が使える
「受託者である子どもが破産をしてしまった場合に、信託した財産が差し押さえられるのか?」という質問を受けることがあります。答えは、違います。信託した財産は、受託者である子どものものではなく、あくまで財産権を持っている親のものです。そのため、子どもの債権者は差し押さえができないルールになっています。これを「倒産隔離機能」と呼んでいます。ただし、信託をしておけば受益者である父親の債権者から信託した財産を守れる、と聞くことがありますが、信託された財産の代わりに「信託受益権」という権利を受益者の父親は持ちますので、受益者である父親が強制執行などを受けた場合には、「信託受益権」が差し押さえられ、信託財産にも影響が及びます。
家族信託のデメリット
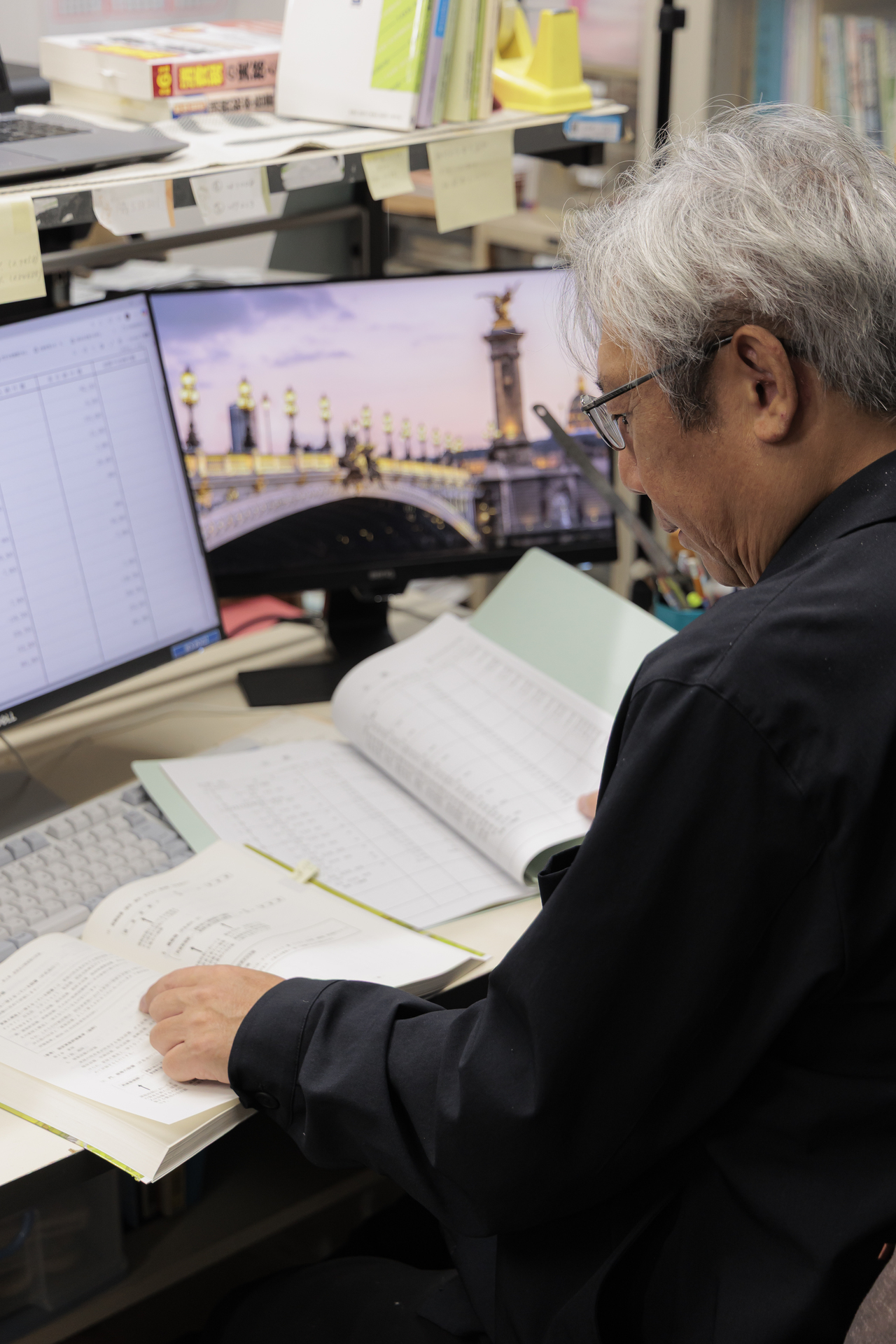
1.身上監護をするには成年後見制度を利用する必要がある
家族信託は万能ではありません。家族信託には身上監護権はありません。これは、認知症になった親が施設に入居する場合、受託者である子どもが親の代理人として入居契約をすることができないということです。家族信託はあくまでも、財産管理のための制度です。入居した施設のお金を信託された財産の中から支払うことはできますが、親の代理人として入居契約をする権限はありません。そのため、身上監護まで考えているのであれば、任意後見契約を結ぶことをおすすめします。任意後見契約とは、子どもや頼れる人をあらかじめ後見人に指定をしておく契約になります。
2.財産の管理を誰もやりたがらない場合がある
家族信託の受託者を誰もやりたがらない場合があります。そうすると家族信託自体ができません。建物を目的とした家族信託の場合には、受託者には建物について管理する義務があります。もしも老朽化して壊れて通行人などに怪我をさせてしまった場合には、その損害を賠償する責任が生じます。信託をされた財産以上の損害だった場合には、自身の財産からも賠償しなければなりません。また、毎年支払う必要がある固定資産税の納税通知書も受託者に届くだけでなく、毎年、受益者である父親に向けて信託された財産の状況を報告する手間も発生します。そういう意味で受託者の責任は重いものになるため、引き受けてくれる受託者が見つからないということも起こりうるのです。
3.親族間の不公平感を生む恐れがある
2人いる子どものうち、1人を受託者とした場合に、他の子どもに何も知らせず勝手に進めてしまうと、知らされなかった子どもから文句が出てくることもあります。受託者である子どもは、信託された財産に対してとても大きな権限を持つため、財産の収支等がブラックボックス化してしまっている場合に、お金を使い込んでいるのでないかという疑いが生まれ、家族間の争いに発展することがあります。それを防ぐためには、あらかじめ家族信託を進める前に家族会議をしておくことが重要です。
4.祖父母や両親に契約の同意を取りにくい
家族信託の主役は祖父母または両親です。そのため受託者候補の子どもの意向だけで進めることはできません。祖父母または両親が家族信託について理解し、進める希望をもらわない限りは進められません。ここで、よく止まってしまう二つの事例を紹介します。一つ目は、わかりづらい制度であることです。家族信託は、「贈与」や「売買」に比べると、日常、頻繁に出てくる契約ではありません。そのため、「よくわからないし、面倒くさそうだからやらない」と言われてしまい、同意が取れないということがあります。また、投資信託と誤解をされてしまい、前に損をしたからやりたくないと言われることもあります。二つ目は、財産が受託者の名義に変わることです。特に不動産の場合に、不動産登記の名義が受託者である子どもに変わるため、生きてる間に不動産をとられてしまうのではないかという不安が生まれ、同意が取れないこともあります。
5.直接的な節税対策にはならない
家族信託それ自体には、相続税を節税する効果はありません。不動産等の名義は子どもに変わりますが、財産権(受益権)は親の元に残るためです。信託したからといって財産の評価を下げることもできません。
親に相続が発生したときには、財産権(受益権)は信託契約で決めた人に承継され、その時に相続税と同様の税額を納付する必要があります。
6. 遺留分侵害額請求をされる場合がある
家族信託契約によって決めた後継者に財産権(受益権)を承継する際に、遺留分を持つ相続人がいる場合、遺留分相当額のお金を請求してくる可能性があります。
遺留分侵害額請求は家族仲を壊してしまうことにもつながる強い権利のため、遺留分が発生しないように設計することや、あらかじめ家族会議をしておくなど、未然に防止できる工夫をとっておくことも重要です。親族仲が悪化する
子どもの1人が親自身や他の兄弟に情報共有をせずに、勝手に進めていくと誤解を受けやすいです。信託をスタートさせるときに財産の名義を変更する手続きが発生したり、相続のときに誰が財産を承継したりするのかも決められる制度だからです。
家族信託の失敗
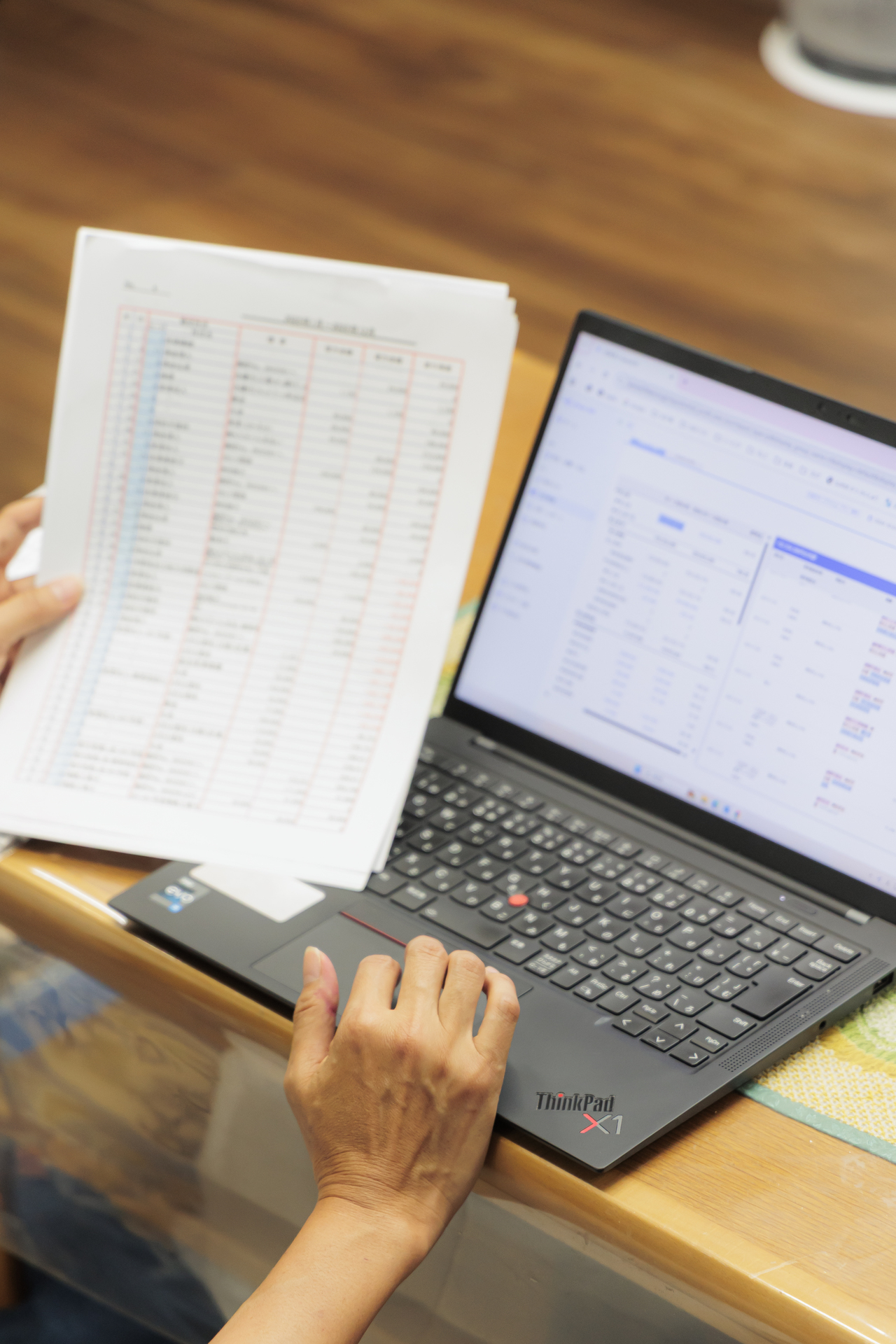
1.親族仲が悪化する
子どもの1人が親自身や他の兄弟に情報共有をせずに、勝手に進めていくと誤解を受けやすいです。信託をスタートさせるときに財産の名義を変更する手続きが発生したり、相続のときに誰が財産を承継したりするのかも決められる制度だからです。
2.信託できない財産を対象にしてしまう
家族信託できない財産があります。代表的なものは「農地」や「預貯金口座」です。これらの財産は、たとえ信託契約書に記載しても効果が生じません。「預貯金口座」は銀行との契約で譲渡禁止特約という約定があり、勝手に名義変更はできません。親と家族信託契約を結び、その契約書を銀行に持っていって「家族信託契約をしたから親の口座の預金を下ろしたい」と言っても銀行側は対応してくれません。ただし、預貯金口座にある金銭は信託できます。この場合、信託契約を結んだ後に、親自身が口座内の金銭を、受託者である子ども名義の信託口口座(家族信託用の口座)に送金手続きをする必要があります。
3.不動産の家族信託で高額な税金が発生
家族信託を契約する場合にも、税金には注意が必要です。例えば、父親が持っている不動産を家族信託して、その財産権(受益権と言います)を孫が持つとする契約をしたとします。この場合、委託者本人ではなく第三者が受益者(信託財産から生じた利益を受ける権利がある人)となるため、他益信託となり、孫に贈与があったものと見なされ孫は贈与税を納めなくてはならなくなります。これ以外でも、信託する財産が不動産の場合には、将来、親の亡くなったのち信託契約を終了させたときにその登記をするための登録免許税がかかります。登録免許税は課税される税率が2パターンあり、契約書の内容によっては高い方の税率が採用されてしまう可能性があります。その差は5倍にもなる場合もあるので注意が必要です。
4.「1年ルール」で強制終了してしまう
財産権を親から子、子から孫に順番に承継させたい場合、遺言では指定することはできませんが、家族信託ではそれが可能です。しかし契約書の構成を間違えると予定外に早く終了してしまい、当初の希望が叶えられなくなります。
その1つが「1年ルール」です。1年ルールとは、受託者が唯一の受益者となり、その状態が1年間継続すると信託契約が終了するというものです。
「受託者=受益者」の場合は、信託ではなく所有権を持っている状態と変わらず、また受託者と受益者が同じ人物という特殊な状態です。これが1年間継続した場合、信託契約は終了すると法律で規定されています。例えば、財産権を親から子、子から孫に順番に承継させる家族信託を契約したとします。親が死亡し、子が受託者と受益者とを兼ねた場合、この状態が1年続くと家族信託は終了となります。
信託契約を終了させず孫の代にも承継していくためには、家族信託を開始するときにあらかじめ第二受託者を決めておいたり、受託者を変更するなど、「受託者=受益者」を解消し1年ルールを回避する工夫が必要です。
5.認知症が進んで信託契約ができなくなる
家族信託は認知症対策の1つですが、親に契約する能力がある間しか契約できません。したがって、家族信託を利用することを決めて、実際に契約の締結までどのくらいのスピードでたどり着けるかも重要になります。
信託契約の内容が複雑になる場合や、融資を受けていて事前に融資銀行に確認が必要になる場合などは、契約の締結までに半年など長期間かかることもあります。その間、親の認知症が進んでしまい契約能力がなくなってしまった場合は信託契約をすることができなくなります。
6.自分たちで契約書を作成してトラブルになる
今は、様々な手続きの流れや必要書類の雛形などをインターネット上で見つけることができるようになり、自分で手続きをする方も増えてきました。しかし、家族信託の契約手続きを自分たちだけで進めることはお勧めしません。
インターネット上で雛形として上がっている契約書には不備のあるものがあります。家族信託は2006年の信託法改正をうけて施行され、まだ十数年しか経っておらず、大変高度な契約です。自分たちだけで契約書の作成を行った場合はこのような不備を発見できず、将来のトラブルを作り出してしまう危険性があります。司法書士や弁護士など専門家に契約書作成を依頼することをお勧めします。
7.遺留分トラブルが起きる
家族信託契約は相続の時の財産の承継についても定めることができるので相続対策としても有効です。しかし、相続人間で偏った割合で財産を承継させる場合には注意が必要です。遺産をもらえなかった相続人から遺留分を請求される可能性があります。
8.損益通算ができなくなる
アパート経営をしている方特有の家族信託での注意点として損益通算があります。損益通算とは、同じ人が所有する赤字経営のアパートの最終的な損失を黒字経営のアパートの最終的な利益と足し合わせて利益を圧縮できるルールのことです。
しかし、家族信託を利用する場合には注意が必要です。なぜなら「信託したアパート」に損失があっても、当該損失は0(ゼロ)とみなされ、「信託していない黒字の不動産」の利益と損益通算をすることができないからです。損益通算が出来なければ、信託していない黒字の不動産の利益を圧縮できずに、所得税がかかってしまいます。
特に大規模修繕などを予定している場合、損益通算について注意して家族信託を設計しないと、損失が使えない分、多額の税金を納めることになりかねません。
家族信託の失敗・後悔を避ける方法
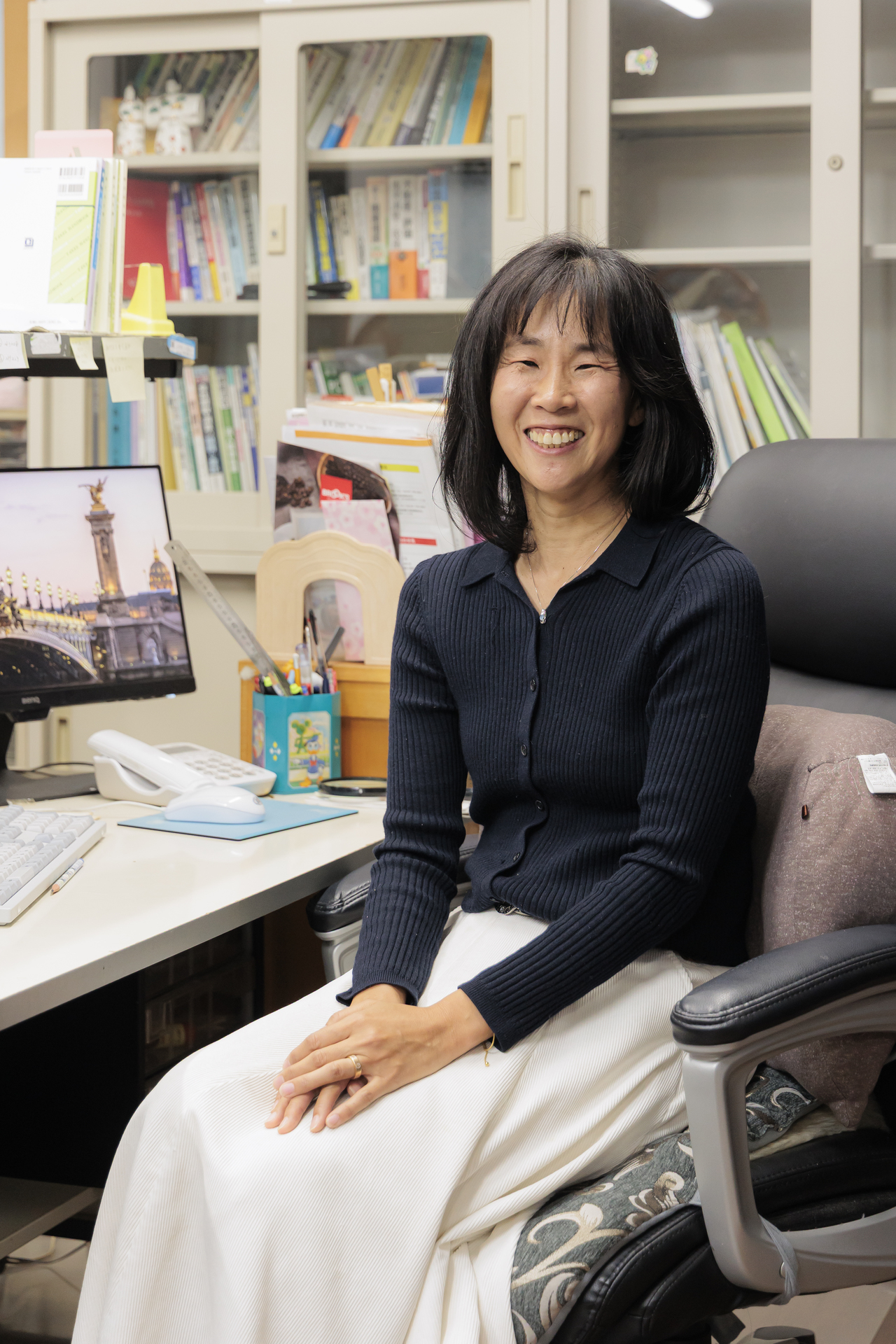
1.専門家に相談する
失敗を回避する1番の方法は、家族信託に長けている専門家を見つけることです。そうすれば、家族信託契約書の不備からの失敗、家族との情報共有の不備からの失敗や税務面での失敗などを回避することができます。
2.親が元気なうちに契約を結ぶ
「認知症が進んで信託契約ができなくなる」で説明したように、親に契約する能力がある間しか家族信託は契約できません。したがって、親が元気なうちに、なるべく早めに行動する必要があります。なお、認知症の程度が軽度であっても、判断能力が十分にあると認定されれば、家族信託を契約できる可能性はあります。とはいえ、後にその家族信託の有効性を巡ってトラブルになる恐れがあります。成年後見制度を利用した方がいいというケースもありえますので、専門家と相談して下さい。
3.家族会議を開き情報を共有する
家族信託を進めるときに、家族会議を開くことも効果的です。親の財産が絡むことなので、知らされていない中で進んでいると感情面での不安が生まれ、トラブルにつながります。そのため、家族会議を開催し、全員の合意を得て、進めていくことがベターです。家族会議では、「家族信託の目的や仕組み」「相続についての考え」を共有します。重要なことは、「親の言葉」で話してもらうことです。子供の1人から、他の兄弟に伝えるよりも、「親の言葉」で伝えた方が、同意が得られやすいです。
4.家族信託以外の相続対策も検討を
親の認知症対策として考えられている家族信託ですが、家族信託だけでは対応できないケースもあります。そのような場合に備えて、遺言や任意後見契約、生命保険など他の方法を組み合わせることもあります。また、ご家庭の状況や目的、資産によっては家族信託が最適でないこともあります。例えば、数百万円程の金銭について子供に管理を任せたい場合には、家族信託ではなく、生前贈与を活用する選択肢もあります。
どの方法がベターなのかを判断することは難しいので、専門家にアドバイスを受けてすすめることがいいでしょう。
家族信託の料金表
| 信託財産に対して | 1%~ |
|---|
※サービス費用の料金について、弁護士・司法書士への依頼費用は別途となります。
家族信託の流れ
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
家族信託の手続きの流れ

- 信託契約を締結する
- 信託口口座の開設
- 信託登記を行う
- 信託財産の管理、運用の開始
信託契約を締結する

委託者と受託者で信託契約の内容について取り決めをして、契約書を取り交わします。契約書に記載する内容はそれぞれ自由に決めて問題ありませんが、主に以下のような事項について取り決めることになります。
- 信託の目的
- 信託財産の範囲
- 財産の管理方法や処分権限の範囲
- 受託者・受益者が誰か
- 信託の終了事由
信託口口座の開設
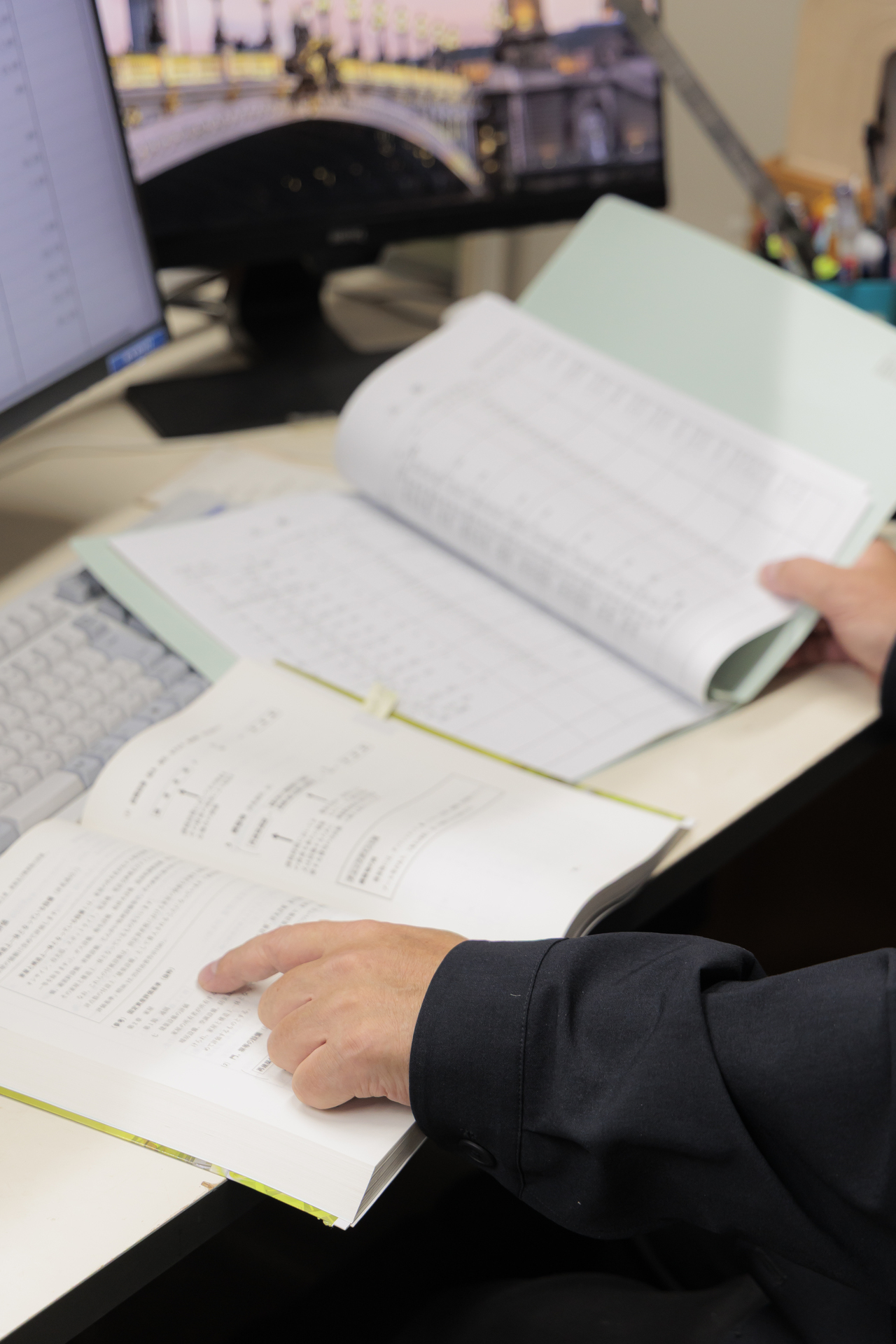
信託財産を管理するためには、信託財産管理用の銀行口座を開設する必要があります。受託者には、自分の財産と信託財産を分別して管理する義務があるためです。受託者自身の生活用口座と分けて管理する方が、あとあと問題になりにくい点もメリットです。なお、信託銀行や銀行、信用金庫の中には、家族信託専用の口座を開設できるところもあります。
信託登記を行う

信託財産が不動産の場合、信託財産であることを公示するために、名義人を委託者から受託者に変更する登記を行う必要があります。登記は法務局で行いますが、個人で対応するのが難しい場合には、司法書士に相談することをおすすめします。
信託財産の管理、運用の開始

ここまでの手続きがすべて終われば、信託財産を管理、運用することができるようになります。それと同時に、信託財産を管理する義務も生じます。
どのようなご依頼があったかを一言で記入

父の認知症が心配になり、家族信託を利用しました。以前は財産管理や将来の相続をどうするか不安ばかりでしたが、信託契約を結んだことで安心感が得られました。自分が受託者となり、父の財産を適切に管理できる体制が整い、銀行手続きや不動産管理もスムーズに進められています。父も「自分の意思を生かせる仕組みだ」と納得しており、家族全員が前向きに話し合えるようになりました。複雑に思えた制度ですが、専門家に相談したことで安心して導入できました。
いかがでしょうか。
このように、当事務所の家族信託サービスなら、適切な財産管理が実現できます。
家族信託に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
新着情報・お知らせ
本田陽一郎公認会計士・税理士事務所

住所
〒669-1133 兵庫県西宮市東山台3丁目4番地11
アクセス
JR福知山線西宮名塩駅から徒歩10分
駐車場:駅前にあり
受付時間
10:00~20:00
(アポがあれば柔軟に対応)
定休日
年末年始・春季・秋季



